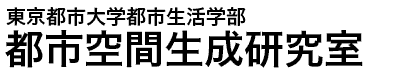【都市景観SDs】今年度も始動しました!

今年も新年度最初のプロジェクトとして、都市景観スタディーズを開始しました。
毎年、新メンバーとともに大学周辺のエリアを1箇所ずつ景観リサーチするプロジェクトです。
今年は東急大井町線で多摩川を越えて、溝の口です!
普段から何かと研究室の懇親会や打ち上げなどでもお世話になっている溝の口。駅周辺の飲み屋街はよく訪れるけれど、あまり周辺の市街地まで足を伸ばしたことはない人も多いはず。
東急線とJR線の結節点である溝の口は、近世までの宿場町から工場誘致して発達した市街地で、工場はその後他地域に移転して、集合住宅や学校などの公共施設などに土地利用を転換しながら現在まで市街地形成してきました。
フィールドワークしてみると、古層としての近世の農村集落や二ヶ領用水などの農業レイヤーの上に市街化していることがわかり、また、工場立地の時期によってそれが用途地域にも影響しており、工場が移転したとしてもその影響がしっかり市街地に現れており、読み解き甲斐のある豊かな文脈を感じるとることができます。
4月24日のフィールドワークはほぼノンストップで3時間ほどで溝の口を踏破しました。
ここから担当エリアを分けて、景観読解から景観形成ガイドラインを提案してまとめます。